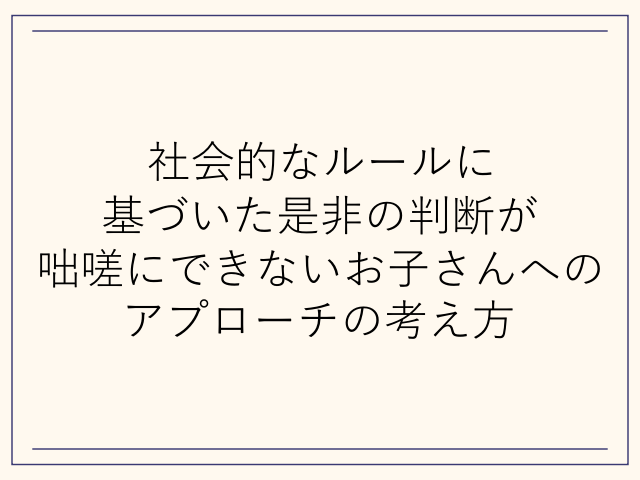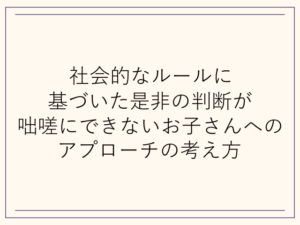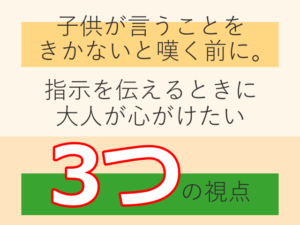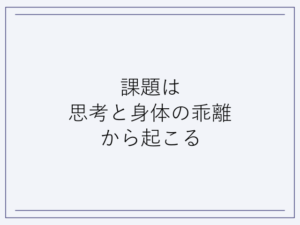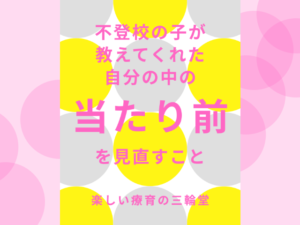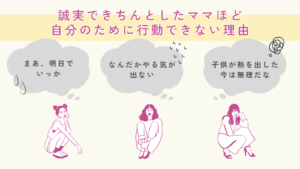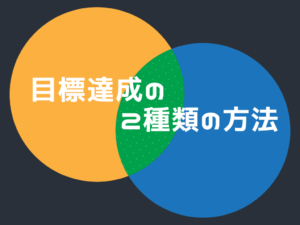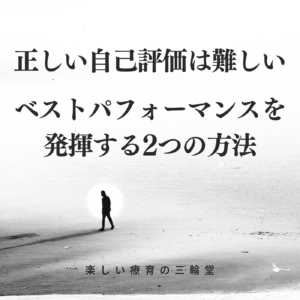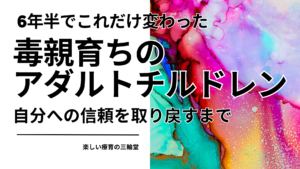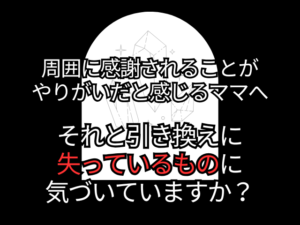723-1 気持ちの揺れと身体のコントロール
以前、こんな記事を書きました。
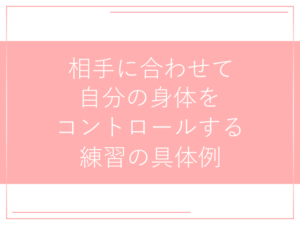
気持ちの揺れに応じて衝動的に身体が動き、周囲との摩擦が起きている場合、相手に合わせて自分の身体をコントロールする練習を取り入れることで、やがては感情面のコントロールもできるようになっていくことが期待できます。
前回の記事で書いたのは、どちらかというと未就学~小学生くらいのお子さんに向いているアプローチです。(中高生以上のお子さんがやって悪いわけではありませんが、ちょっと子供っぽくて抵抗を感じる方もいるかも、という意味です)
アプローチ方法の原則は、何歳の方に対しても基本は同じです。
が、年齢を重ねるほど、その人オリジナルの経験、思考の癖、心の傷、身体の特徴が積み上がっていくので、お伝えする際には工夫が必要になってきますね。
723-2 良い/悪いを咄嗟に判断する力
学齢が上がるにつれて、だんだん世間と折り合いをつけて過ごせるようになってくるので、衝動的に身体が動いて困る人は減ってきます。
中高生以上のお子さんに関するお困りごとでは、乱暴に手足が出てしまうというよりは、「良いこと」と「悪いこと」の判断が瞬間的につかないせいでトラブルを起こしている、という事例が増えるように思います。
ここでいう「良い/悪い」とは、人の身体が本来持っているものというより、後天的な指導によって身に着ける価値観のことです。
たとえば交通ルールを守る、飲酒喫煙の法的ルールを守る、その場(学校、会社、公共の場など)にふさわしい言動をとる、といった社会的なルール・マナーがその一つです。
723-3 ルールがとっさに思い浮かばないこともある
たとえば、お友達にそそのかされて万引きをしてしまった子がいたとします。(仮定の事例です)
このとき、万引きが良くないことだとご本人が知らなかった場合は、丁寧にルールを教えてあげる必要があります。
また、お友達に恰好をつけたい、大人に反発したい、などの理由でその子があえて悪さをしている場合は、お子さんの心に目を向けたサポートが必要になります。
本人はやりたくなかったけれどもお友達に強要されて仕方なくやった場合など、人間関係や環境設定に目を向けてあげたい事例もあります。
難題になりがちなのは、万引きはダメだと知っているはずなのに、その場でお友達と話し合っていると、ルールがとっさには頭に思い浮かばないお子さんの場合です。
長くなりましたので、続きは次回に。
本日は以上です。
それでは、また。
いつもあなたに明るい風が吹きますように。