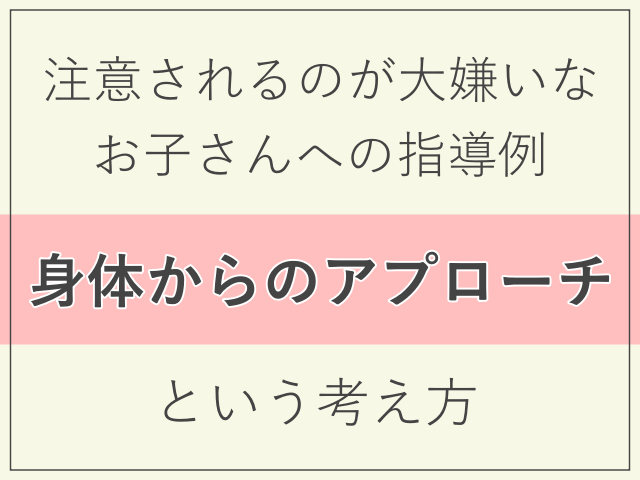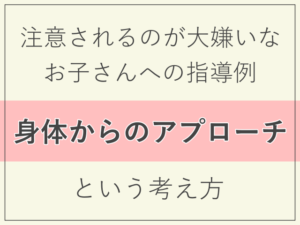注意されると反論したくなるお子さん
「注意されると徹底的に反論したくなる」タイプのお子さんについて、Mさんからこんなご相談をいただきました。
一部抜粋してご紹介します。
人格障害、自閉症スぺクトラムのお子さんについて。
注意をされると意地でも自分を正当化しようと言葉巧みに言い訳をしてきます。
悪いことや都合が悪いことをしても認めません。
駄目なことは駄目だったり、他人に謝ったり、自分の行った悪い行動を認めさせたりなどの事を教えたり、行動させたりしたいのですが苦戦しています。
苦戦しているからといって、その子に勝ち誇らせているわけではないのですが、その子は、勝たないと意味がないと言って、注意を受けると反省することよりも注意をする人に勝ちたいという考えが強いです。
私は、その子の言い分も聞いた上で、悪いことは悪いと教えたい、伝えたい。
別の方は、その子の今までの養育環境のせいで今こうなっているのだから、悪いことは悪いと教えるだけにして、大人にますます不信感を作らなくても良いのではないか? と言っています。
どのような過去を背負っていても悪いことは悪いと教えなければいけないと私は思っています。
ご相談の文面から、Mさんが真正面からお子さんと向き合おうとしておられる姿勢が伝わってきました。
こうして真剣に子供たちと向き合ってくださる先生方の存在がどれほどありがたいことか・・・
わたし自身も一人の保護者として、そして一人の人間として、心から感謝を申し上げます。
言葉が対立を引き出すこともある
こちらのお子さんがどんな育ち方をしてきたかは想像するしかありませんが、きっとご本人も周囲の大人たちも、いろいろな苦労をされてきたのでしょうね。
「良い/悪い」
「勝ち/負け」
「正義/悪」
といったように、単純な二項対立で物事を捉えがちな子供たちがいます。
そうした子供たちは、白か黒か、0か100かといった鋭利な物差しで物事を切り分けるので、結果として周囲の人々と社会的にぶつかり合うことが多くなりがちです。
今回ご相談のお子さんも、そうした傾向がありそうですね。
「言葉巧みに言い訳をする」とも書かれていますので、言語を使いこなす能力は人並み以上にお持ちのお子さんなのだろうと思います。
こういうタイプのお子さんには、言葉で指導しようとすると、言葉で戦うという反応を引き出してしまいます。
身体で伝える
そうした場合にお勧めしたいのが、
身体で伝える
というアプローチです。
言葉は物事を単純に切り分けるのが得意ですが、身体は物事を全体的に受け取ります。
言葉を一旦脇に置いて、身体に目を向けてみましょう。
身体を整える
わたしたちは自分の身体を通して世界を理解しています。
ですから、身体に入ってくる信号のどこかに滞りがあると、世界の理解の仕方に何らかの歪みが生まれる可能性があります。
今回ご相談のお子さんは、人格障害と自閉症スペクトラムの診断を受けているということでした。
自閉症の方の中には、身体図式に特性のある方が多くいらっしゃいます。
今回のお子さんについても、身体のどこかに、極端な筋緊張があったり、逆にダランとした部分があったり、手足の使い方がうまくいっていなかったり、食事・睡眠・排泄に何らかの違和感があったり、する箇所がないでしょうか。
そういった身体の様子を見守って、お子さんの身体のクセをつかみ、こわばりや緊張を整えてあげると、お子さんの物事の受け取り方が変わり、結果として行動を改善できる可能性があります。
ぜひ、日常生活をよく観察してみてください。
身体に意識を向けてみる
周囲とぶつかり合うにおいては、ご本人にもいろいろな言い分があると思うのですが、自分の感情や行動をコントロールして、柔軟に身をこなしながら過ごせたほうが、社会的な風当たりはよほど弱くなりますし、はるかに生きやすくなります。
そうした柔軟性を身に着けるためにも、言葉を手放して身体に意識を向けることをお勧めします。
身体に意識を向けるための運動の例「スクワット」
たとえば、大人と一緒に「スクワット」をしてみてはいかがでしょうか。
スクワットは、全身が動くわりに身体の移動が少ないので周囲に影響を与えにくく、それなりにきつい運動なので心身をしっかり動かすことができます。
また、手を頭の上に組む、膝を曲げるなど、動作が左右対称でわかりやすく、比較的模倣しやすい運動でもあります。
「スクワットしよう!」などとごく簡潔な声かけをして、大人が率先してやってみせます。
ご本人にとってちょっときついと感じるくらいの回数をやると良いかと思いますが、年齢・体格・身体能力に応じて調整してください。
スクワットによって生まれる身体感覚
こうした強めの運動をすることで、意識が自分の身体に向かいます。
これを読んでくださっているあなたも、可能ならば今ちょっとだけ、スクワットをしてみてください。
10回もやると、だいぶ太ももの前のあたりが疲れてきませんか。
息が多少上がって、大きく呼吸をするので、全身がじわーっと温かくなって、どこか爽快な感覚になりませんか。
今まで仕事のことなどで悩んでいたことを、一瞬忘れませんでしたか。
お子さんに伝えたいのはこの身体感覚です。
身体に意識を向けるサポートとして言葉を使う
お子さんは最初は戸惑うでしょうが、少しずつ、自分の身体に意識を向けられるようになっていきます。
大人が言葉でサポートするのは、身体に意識を向けさせる方向づけのみでOKです。
たとえばお子さんの息が上がっているようだったら、「ハアハア言うね」「スッキリしたね」などと表現してあげたり、脚が疲れたようだったら、太ももの前あたりを大人がそっと手で押さえて、「ここが疲れたね」「重くなったね」などと筋肉の感覚を表現してあげたりして、ご本人が身体の感覚に意識を向けられるようにサポートしましょう。
身体感覚が整うと社会的にも変化する
こうした身体感覚の育みによって、
- 感覚過敏が和ぐ
- 攻撃的な言動が減る
- 気持ちのコントロールが上手になる
- 集団行動にうまく参加できるようになる
といった変化の例があります。
また、大人の側も、お子さんに対する見方が変わります。
なんとなく心の焦りやこわばりが取れて、落ち着いたニュートラルな目でお子さんを見られるようになると思いますよ。
お子さんの事情、発達特性、周囲の人的・物的環境などによって、ベターな関わり方はそれぞれ違います。
本記事はあくまでもご参考としてご覧いただき、目の前のお子さんに合った支援を工夫していただければと思います。