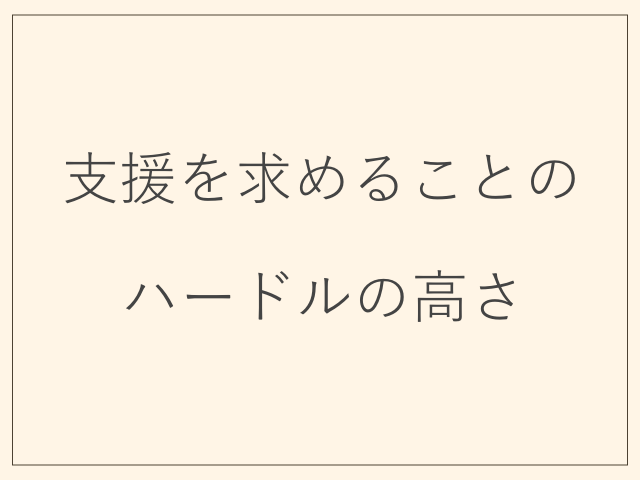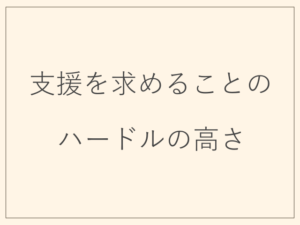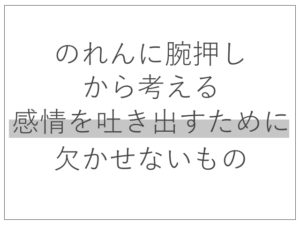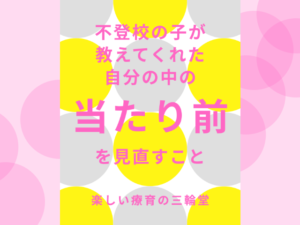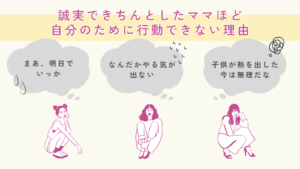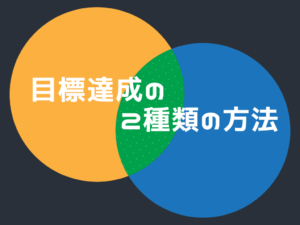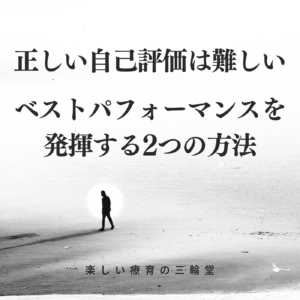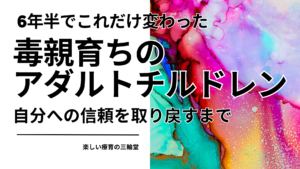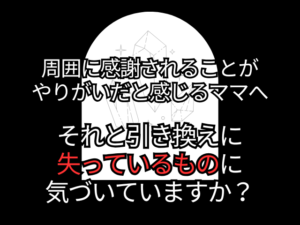606-1 ▼ 援助や支援を求めることの前提
前回は、もしGW後に登校渋りがあったならば、お子さんと話し合い、学校に相談してみてくださいと書きました。
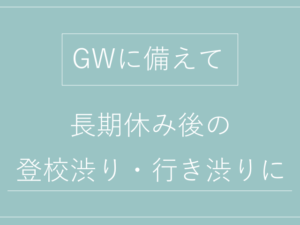
この「話し合う」「相談する」という局面から少し話を広げてみます。
誰かに相談して援助や支援を求めることは、実は意外と難しいものでもあります。
なぜなら、誰かに相談するときには、そもそもの前提として「相手との信頼関係」がなければうまくいかないからです。
606-2 ▼ 支援を求める=自分の弱さと向き合う
支援を求める、助けを求めるということは、
- 自分の苦手な面、弱い面、うまくいっていない面と向き合うこと
- それを第三者にさらけ出すこと
であります。
人によっては非常に強い心理的なハードルを感じる場面です。
相談する側は、緊張や不安、時にはそれが転化した怒りや悲しみを覚えるかもしれません。
悪くすれば、「できない自分」と向き合うことが、自己肯定感を下げる結果にもつながりかねません。
606-3 ▼ 自分の思いを表現しても大丈夫と思える関係性を
だからこそ、信頼できる相手が受け止め、支えることが何よりも大事になってきます。
もしその人の苦手さの背景に障害特性が隠れている場合は、障害特性を論理立てて科学的に学ぶことで、「できないのは自分が悪いからではない」と理解していくことも大切ですね。
この場・この相手となら、自分の思いを表現しても大丈夫なんだという気持ちが育まれて初めて、本当の意味での相談や支援がスタートします。
大人は気軽に子供たちに「なんでも相談してね」と言いますが、自分は相手にとって「なんでも相談」できるような存在になれているのか、相手との関係性の中で「なんでも相談」できるような信頼関係が構築されているのかを常に振り返りたいものです。
深い自戒を込めて。
本日は以上です。
それでは、また。
いつもあなたに明るい風が吹きますように。