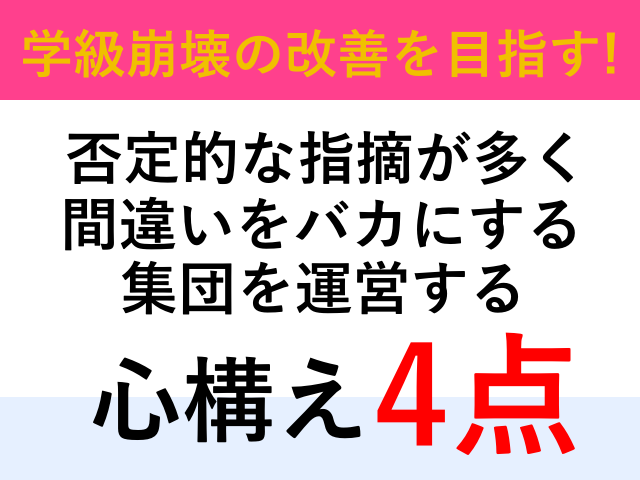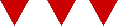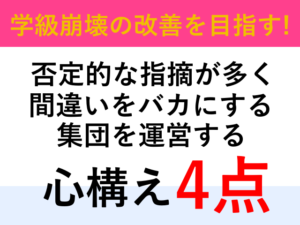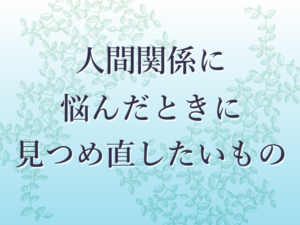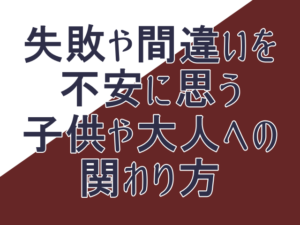494-1 ▼ 難しい学級の事例
ある小学校の先生の事例発表に、こんなことが書かれてありました。
いわゆる「難しいクラス」を立て直すにはどうすればよいか、という心構えです。
事例
- 学級崩壊に近い、難しいクラスがある。
- 担任教諭は客観的に見て学級経営が上手なほうではない。
- 担任のコミュニケーション能力は低い。
- 生徒たちからは担任に対する不満が聞かれる。
- 生徒たちはお互いに悪いところを指摘し合うようになっている。
- 間違ったりできなかったりすることをお互いにバカにし合うような空気がある。
- 生徒たちの不満の声や雑多な雰囲気に追われて、クラス内に在籍している、特別な配慮が必要な児童に手が回っていない。
(たまたまその児童が自己主張をしないタイプの子だったこともありほぼ完全放置に近い)
※複数の事例を取り混ぜて一般化されています
494-2 ▼ クラス運営の心構え
上記の事例は、特定のクラスを指すものではありませんが、こういう雰囲気のクラスは実際、(うーん、あるかも・・・)と思わざるを得ません、残念ながら。。
小学校の学級に限らず、大人の世界にも、こうした空気感のギスギスした集団があったりするのではないでしょうか。
こうした事例に対して、冒頭の小学校の先生は、以下のような心構えで臨むべきと書かれています。
(わかりやすくするために瀧本が一部編集しました)
1.理想を捨てる
教師が自分の理想を掲げて子供たちを引っ張ったり呼び寄せたりしようとするのでなく、一旦理想を捨てる。
目の前の子供たちの現在地に立ち、得意なことやできることを探して承認し、背中を押す指導から始める。
2.「やろうとしたら」褒める
やったら褒める、ではなく、やろうとしたら褒める。
その瞬間を逃さないこと。
ざわついた環境では、子供が望ましい姿を持続することが難しい。
「やり終わるまで待ってから褒める」ような余裕はないと心得たほうがよい。
3.部分を積み上げる
学級経営もコミュニケーションも、急にはうまくならない。
一度失った子供たちとの信頼関係もすぐには戻らない。
すべてを一度に改善しようとせず、「一部分だけは確実にできた」を積み上げていく。
教師自身も、できない自分を責めるのではなく、「ここはできた」自分を承認していく。
4.前向きな空気を作る
ネガティブ報告は受け流し、ポジティブな報告を期待する旨を伝える。
ポジティブ報告があったら、行為者だけでなく、報告者も褒めるようにする。
意欲的な子を褒め、それを真似して良くなっていく子にも「真似して良くなるのは最初からできているのと同じくらい価値があること」という価値観を伝え、良い行為の伝播を促す。
494-3 ▼ あらゆる集団に活用できる原理原則
以上、心構えの4点です。
小学校のクラスだけでなく、家庭、夫婦関係、職場のチームなどなど、ありとあらゆる集団での関わり合いにとって意義のある考え方ではないかと思いましたので、シェアさせていただきました。
この事例報告は、身体がもっとも自然に本来の力を発揮する法則である「身体の原理原則」にもよく当てはまります。
現在地に立つ
1つ目の「理想を捨てる」という視点は、身体の原理原則では「現在地に立つ」として重視しているポイントです。
理想を描くことが悪いわけではありませんが、頭が描く理想図と身体が実際に存在している現在地とを比べた場合、身体がより自然に動くのは、現在地からスタートした場合です。
理想からスタートした動きは、良くて想定の範囲内にとどまり、悪くすれば相手の反発や抵抗すら招きますが、現在地からスタートした動きは、のびのびと発展していきます。
動いているところから動く
2つ目・3つ目の「やろうとしたら褒める」「部分を積み上げる」という視点は、身体の原理原則から見ると「動いているところから動く」という法則に当てはまります。
これは、頭で考えて身体をその通りに動かそうとすることと、自然に身体が動いているところをキャッチしてその動きに乗っていくことの違いです。
前者は、自分の想定の範囲内での繰り返しで終わります。
後者は、自分でも思いがけない発展を見せます。
「頭」を「自分」「大人」「教師」、「身体」を「相手」「子供たち」「集団」などと読み替えてみると、頷かれる部分もあるのではないでしょうか。
良い悪いは存在しない
4つ目の「前向きな空気を作る」に関しては、身体の原理原則から見ると、これは「過程」であり、これが完成形ではないと言うことができます。
良い・悪いの価値判断をするのは「頭」であって、「身体」に起こることには、良いも悪いも存在せず、すべてはバランスを取っているだけです。
たとえば今回の事例のように、ポジティブな空気のみをキャッチし続けると、子供たちがネガティブな思いを吐き出しにくくなり、ポジティブを装うようになったり、ネガティブな発想を抱く自分や仲間を否定するようになったりもしかねません。
ただし、今回は、クラスにはすでにネガティブな空気感が蔓延していたということでしたので、一旦その逆のポジティブに思い切り振れてみる(一旦逆に行ってバランスを取る)のはとても良い手です。
ポジティブに振れたあと、自然に生まれてくるネガティブな意見も否定せずに受け止め、話し合えるような空気感が広がっていくと、ますます成熟したクラスに育っていくのではないかなと思います。
このように、身体の原理原則を活用すると、学級運営のように集団内の複雑な相互コミュニケーションが行われる場でも、「こんな場合にはどうすれば良いか」を考える明確な指針を持つことができます。
身体の原理原則をもっと知りたいと思われたら、こちらのページをご覧ください。