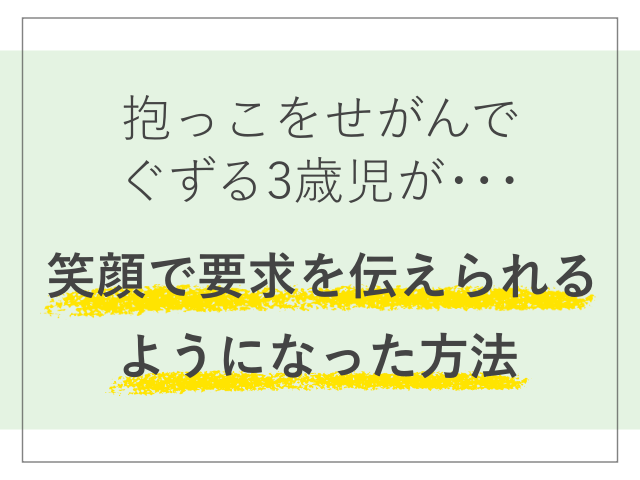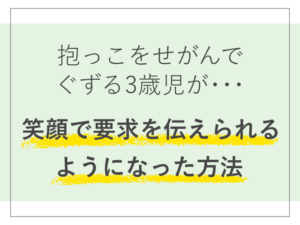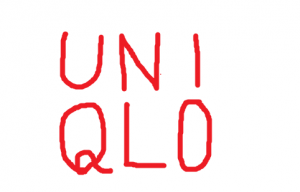外出中に泣き叫び始めた3歳児
当時1歳の娘と3歳の息子をつれて、家族で外出したときのことです。
家を出た直後から妹とベビーカーを取り合って機嫌が悪くなった息子。
しばらくなんとか歩いていましたが、だんだん抱っこ抱っことぐずり始め、ついに大声で泣き叫び出しました・・・
こうなるともうサイアクですよね(小声)
泣き声に親もイライラしますから、気の短いパパさんがいつ爆発するか、母は内心ヒヤヒヤハラハラです。
そこで、ちょっと考えて、療育のコツを応用してみることにしました。
親子がご機嫌になるために活用した療育のコツ4つ
今回は、「今、抱っこを我慢できたら、近い将来に、我慢したことの報酬を与えます」という戦略を考えました。
療育のコツ その1
自分が泣いているときは人の話が聞こえない
人の声の聞こえ方には、「骨導」と「気導」の2種類があります。
- 骨導=自分の声が頭蓋骨を伝わって聞こえる音
- 気導=自分の声が周囲の空気を伝わって耳から聞こえる音
自分が声を出している時は、骨導で自分の声が響き渡っているので、他の音は聞こえていません。
大人はいろいろなスキルや経験則を駆使して、自分が話しながらでも他人の話を理解できますが、幼い子供はまだそれができません。
ですから、子供に話を伝えたい時は、「まず本人に黙ってもらう」必要があります。
そこで今回は、まず立ち止まり、自分がしゃがんで、息子の肩をおさえて息子も立ち止まらせ、視線を合わせ、「ママのお話を聞いて」と声をかけました。
泣き方がひどい時はいったん抱き上げるなどして泣き止ませる必要があったかもしれませんが、今回はこれである程度静かになりました。
療育のコツ その2
子供は遠い将来の報酬にはピンとこない
たとえば、
1年後に□□大学に合格することを目標に、毎日勉強する
このような目標を掲げて、毎日地道に勉強することができるようになるには、
- 先の見通しを立てることができる
- 長い時間の概念を把握している
- 努力が報われる経験を蓄積している
このような土台が必要です。
1年後のために今がんばれるのは高校3年生だからであって、3歳児には無理です。
その子なりに理解できる「我慢すべき時間の単位」「効果的な報酬」を考える必要があります。
そこで今回は、「 “抱っこ抱っこ” って泣いて大きい声を出さないで、静かに10かぞえられたら、抱っこしてあげる」と働きかけました。
すでに10分くらい泣いていたので、息子の心がこれ以上耐えられる時間はあまり長くないと判断しました。
また、ちょうど息子は1から10までの数唱ができるようになりつつあったので、本人が把握しやすい「時間的遠さ」だと考えました。
この場合の効果的な報酬は、抱っこ以外にはありえませんので、こちらの希望としては「抱っこではなく歩いてほしい」のですが、ひとまず抱っこを約束しました。
療育のコツ その3
子供は楽しくないと動かない
何事も、楽しくないと、積極的に行動する気持ちにはなれないものです。
大人は理性で自分をコントロールして、楽しくないことでも淡々と作業ができますが、子供にこの自制を求めるのは基本的には難しいと考えたほうがよいでしょう。
息子は数字に興味を持ち始めていて、目に入る数字を指さして読んでみたり、ひとりごとのように1から10まで数唱をしてみたりなど、数に関心が高いことがわかっていました。
「10かぞえよう」と本人が興味を持っている事柄に関連づけることで、前向きな気持ちを引き出そうという狙いで働きかけました。
療育のコツ その4
成功体験が何より大事
がんばろう、努力しよう、と思えるようになるためには、まず「がんばったら、報われた」という成功体験を蓄積することが欠かせません。
「今、抱っこを我慢できたら、近い将来に、我慢したことの報酬を与えます」
という戦略のうち、「我慢したことの報酬を与えます」の部分が、今回の成功体験になります。
最初は半信半疑かもしれませんが、これをやったら本当に抱っこしてもらえた、という信頼ができると、子供の行動は一気に落ち着きます。
今回は、10かぞえながら一緒に歩き、かぞえ終わったらすぐ抱っこしてあげました。
ここで「あともう1歩ね」などと引き伸ばすことは絶対に避けましょう。
以上の働きかけによって、息子は、グスングスンと息をのみながら、必死に泣き声を我慢して、10かぞえる私に合わせて歩いてくれました。
かぞえ終わったらすぐに抱き上げました。
とたんに息子は堰を切ったように泣き出し、しがみついてきました。
母も思い切り抱きしめました。
よくがんばったね!
笑顔で要求を伝えられるようになった
泣き止んでから、「もう下ろしていい?」と聞いてみると、「ヤダ」というお返事です。(^ ^;)
「じゃあ、あの角を曲がったらいったん下りてね。また抱っこしてほしくなったら10かぞえてあげるからね。」
と働きかけて、角を曲がったところで下ろしました。
数歩進むとすぐに、「抱っこ!」の要求が。
このときは、本人の中に「10かぞえたら抱っこしてもらえる」という約束事ができかかっているので、大人はこれを拒否してはいけません。
「じゃあ、10かぞえようね」と声をかけて、数唱を始めます。
このとき、可能なら子供にも声を出してかぞえてもらうとよいですね。
楽しさが感じられ、約束に積極的に関わっていく姿勢ができます。
わたしは数にあわせて息子とつないでいた手を大きく前後に振り、楽しさを演出しました(本人もニコニコ笑っていました)。
これを何回か繰り返すと、だいぶ気持ちも落ち着いて、自分で歩く元気が出てきます。
(この時は、パンを食べたり、電車に乗ったりと、違う活動がはさまったので、それも気持ちを切り替えるのに役立ちました。)
だんだん抱っこの回数は減り、振り返れば、ほとんどの道を自分で歩き通すことができました。
その子に合った働きかけを工夫してみてください
驚いたのは、「ねえ、数かぞえて」という表現で抱っこを要求してきたことです。
今回の働きかけが息子の心に届いたことが感じられました。
もちろん喜んで10までかぞえて抱っこしました。
抱っこ抱っこ!と泣かれてしぶしぶ抱っこするより、楽しいゲームのような関わり合い方で抱っこするほうが、大人にとっても楽しいですよね。
お子さんの個性によって、どんな働きかけが効果的かは変わってきます。
お子さんの個性を一番よくご存知の親御さんだからこそできる工夫がたくさんあるはずなので、ぜひあなたのお子さんに合った働きかけを考えてみてくださいね!