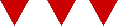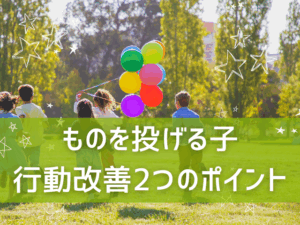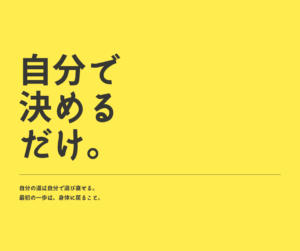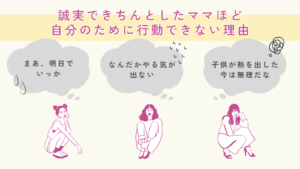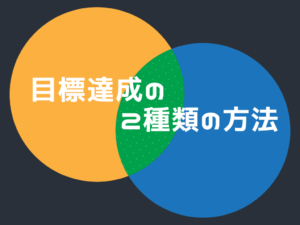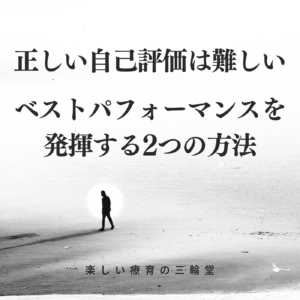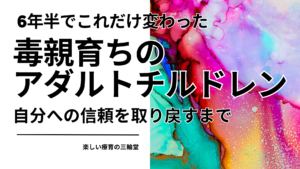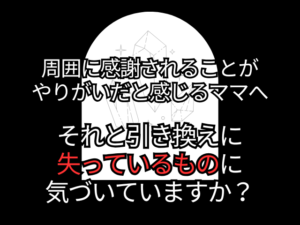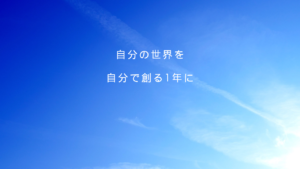お友達に乱暴をする2歳半の男の子
2歳半のS君。
お友達の気を引きたくて、相手を叩いたり、ものを投げつけたりと、乱暴なアプローチをしてしまいます。
先生方は、
「おもちゃを投げません」
「”一緒に遊ぼう” と言うんだよ」
と、丁寧に指導を続けていますが、S君の年齢的にも、まだ言葉よりも身体のほうが先に動く傾向があり、なかなか行動が改善されませんでした。
それに対する先生のアプローチは
そこで、先生方はこんなアプローチを工夫されました。
- 新聞紙を破いてビニールプールに入れる
- 中に入って新聞紙を投げたり散らしたり
- 最後はゴミ袋に新聞紙をぎゅっと詰め込む
という遊びを提案したところ、子供たちは大喜び (^ ^)
プールには、お手玉や、小豆を入れて膨らませた小さな風船なども入っていて、宝物を見つけるような楽しさや、質感の違うものを放り投げたり落としたりする体感も味わえる遊びでした。
S君もお友達もみんな一緒に夢中で遊びました。
この遊びをした日は、S君の乱暴な行動はほとんど出なかったということです。
満たしたいエネルギーは何か? を考える
子供が困った行動をするとき、その子はなんらかのエネルギーを満たしたくてその行動を取っています。
それを「困った」と見るのは、社会や大人の都合に過ぎません。
その子は、自分の自然なエネルギーに従って動いているだけなのです。
その子の満たしたいものを汲んであげれば、「困った」はなくなります。
エネルギーを見極める2つのポイント
ここで言う「エネルギー」とは、主に
- 感情
- 動きの種類、方向性
の2つで現れることが多いです。
たとえばS君の行動の裏には、お友達と遊びたいという感情が隠れていることは明らかです。
また、S君のようにものを投げることで相手にアプローチしようとする子は、ものを落としたり投げたりする動作が好きだったり、ものが重力に従って動く様子を味わうことを好んでいたり、する可能性があります。
実際、S君は、砂場で砂やバケツを投げるのが大好きだったそうです。
周りのお友達に砂がかかったりバケツが当たったりして問題視されていましたが、担任の先生が見る限りでは、
(S君は誰かに当てたいわけではなく、砂の舞う感触や着地の衝撃で砂に沈むバケツの感触が好きなのではないか)
と感じられていたということでした。
行動を変えようとするのではなく、エネルギーを満たす工夫をする
S君は、新聞紙プール遊びによって、
・ものを投げるのが好き
・お友達と遊びたい
これらのエネルギーが満たされ、「困った」行動が消失しました。
「困った」行動を取る必要がなくなったわけですから、当然のことです。
もちろん、一度の新聞紙プール遊びだけで、お友達との関わりがすべて改善されるわけではありません。
継続してアプローチしていく必要はありますが、アプローチの方向性として、
困った行動を叩きのめして無くしてしまうことを考えるのではなく、エネルギーを適切な形で満たす
ことを考えてあげたほうが、はるかに効果的です。
困った行動を改善する2つのポイント
お子さんの「困った」に悩むときは、ぜひ、
- 行動の奥にある感情を満たす
- (より社会的に適切な)似た動きを提案する
これを考えてみてください。
きっと打開策が見つかりますよ。
それでは、また。
いつもあなたに明るい風が吹きますように。